SDGs(持続可能な開発目標)は、世界共通の目標として、私たちの社会や環境に大きな変革をもたらすことを目指しています。しかし、これらの重要なテーマを人々に伝え、理解してもらうことは常に容易ではありません。特にプレゼンテーションの場では、聴衆の関心を引きつけ、メッセージを効果的に伝えることが求められます。
この記事では、「SDGs プレゼンしやすい テーマ」を選択し、その伝達をより効果的にする方法に焦点を当てています。SDGsに関する情報を広めることの重要性を理解しながら、プレゼンテーションを成功に導くためのテーマの選び方や、聴衆の注意を惹きつける技術について掘り下げていきます。
- SDGsの中で特にプレゼンしやすいテーマの選び方
- 効果的なプレゼンテーションを行うためのコツとテクニック
- 聴衆の関心を引きつけるためのストーリーテリングの重要性
- SDGsに関する情報を分かりやすく伝えるためのビジュアル資料の活用方法
【関連記事】省エネで生きる: 家計に優しい10のエコ生活ヒント
SDGsプレゼンで聴衆を魅了!しやすいテーマ選びと成功の秘訣
- 17のゴールから最適なテーマを選ぶ: 聴衆と目的を明確に
- 身近な問題から始める: 共感を得て行動を促す
- データで説得力を持たせる: 信頼できる情報で裏付ける
- ストーリーで共感を得る: 人の心を動かす語り口
- ユニークな切り口で差別化する: 記憶に残るプレゼン
17のゴールから最適なテーマを選ぶ:聴衆と目的を明確に
1. ターゲット層を明確にする
- 年齢層、性別、職業、関心事など、聴衆の特徴を把握
- 聴衆にとって身近な問題や興味のあるテーマを選ぶ
例
- 高校生向け: 進路選択に役立つSDGs関連の仕事や資格について
- 企業向け: SDGsへの取り組みが企業価値向上に繋がる理由と具体的な方法
- 地域住民向け: 地域におけるSDGs課題と解決に向けた住民参加型プロジェクト
2. プレゼンの目的を定める
- 知識の伝達、行動の促進、意識改革など、目的を明確にする
- 目的に合致したテーマを選ぶ
例
- 知識の伝達: SDGsの17のゴールとターゲットについて分かりやすく説明
- 行動の促進: 聴衆が日常生活でできるSDGsへの取り組みを紹介
- 意識改革: SDGsの重要性と緊急性を訴え、問題意識を高める
3. SDGsの17のゴールとターゲットを理解する
- 各ゴールの内容、ターゲット、現状、課題などを把握
- 目的と聴衆に合ったゴール・ターゲットからテーマを選ぶ
例
- ゴール3:すべての人に健康と福祉を
- ターゲット3.4:2030年までに、伝染性疾患による死亡率を3分の2削減し、非感染性疾患による死亡率を3分の1削減する
- ゴール4:質の高い教育をすべての人に
- ターゲット4.1:2030年までに、すべての子どもたちが、質の高い幼児期教育を受けられるようにする
- ゴール13:気候変動に具体的な対策を
- ターゲット13.2:2020年までに、気候変動に関するすべての国の能力強化を支援し、温室効果ガスの排出削減に向けた国家戦略を策定し、実施する
4. テーマを絞り込む
- 広すぎるテーマは、内容が薄っぺらになる
- 具体的な事例やデータを用いることで、説得力のあるプレゼンになる
例
- テーマ: プラスチックごみによる海洋汚染
- 絞り込み: ペットボトルの回収率向上
- テーマ: 教育格差
- 絞り込み: オンライン教育による途上国の子どもの学習機会の改善
- テーマ: 貧困
- 絞り込み: マイクロファイナンスによる貧困層の起業支援
5. 自分自身の関心や経験も考慮する
- 自分自身が興味を持っているテーマは、熱意を持って伝えられる
- 自身の経験に基づいた事例は、聴衆の共感を呼び起こす
例
- 自身の関心: 環境問題
- テーマ: 地球温暖化による海面上昇の影響と対策
- 自身の経験: 海外ボランティア活動
- テーマ: 開発途上国の教育問題と解決に向けた取り組み
- 自身の専門知識: 経済学
- テーマ: SDGs達成に向けた経済政策
■_■/ プレゼン装置はコチラから↓///
■■Amazonで見る身近な問題から始める:共感を得て行動を促す

1. 聴衆の日常生活に関連する問題を取り上げる
- 聴衆が自分自身のこととして捉えられるような問題を選ぶ
- 例:プラスチックごみの削減、食品ロスの削減、エネルギーの節約など
例
- テーマ: プラスチックごみの削減
- 具体的な問題: 買い物袋やペットボトルなどのプラスチックごみの増加による海洋汚染
- 共感を呼ぶポイント: 自分たちの生活習慣が環境に与える影響
- 行動を促す提案: マイバッグやマイボトルの利用、プラスチック製品の使用量削減
- テーマ: 食品ロスの削減
- 具体的な問題: 消費される前に捨てられる食品の量が多い
- 共感を呼ぶポイント: 毎日捨てている食べ物が世界の飢餓問題に繋がっている
- 行動を促す提案: 食べ物余りの献立作り、賞味期限の確認、フードバンクへの寄付
- テーマ: エネルギーの節約
- 具体的な問題: 電気やガスの無駄遣いによる地球温暖化
- 共感を呼ぶポイント: 電気代やガス代の節約にも繋がる
- 行動を促す提案: こまめな電源オフ、省エネ家電への買い替え、公共交通機関の利用
2. 地域や業界における課題を取り上げる
- 聴衆が住んでいる地域や働いている業界における課題を取り上げる
- より身近な問題として共感を得られる
- 例:地域における高齢化問題、業界における人材不足問題など
例
- テーマ: 地域の高齢化問題
- 具体的な問題: 高齢者の増加による介護人材不足、医療体制の逼迫
- 共感を呼ぶポイント: 地域の高齢者は自分たちの家族や地域社会の未来に関わる存在
- 行動を促す提案: 高齢者との交流イベントへの参加、ボランティア活動への参加
- テーマ: 業界における人材不足問題
- 具体的な問題: 働き方改革や多様性の尊重への対応
- 共感を呼ぶポイント: 業界全体の競争力向上にも繋がる
- 行動を促す提案: 女性や外国人材の活躍推進、柔軟な働き方の導入
3. 個人や企業の取り組みを紹介する
- SDGsの課題解決に取り組んでいる個人や企業の事例を紹介
- 聴衆に具体的な行動のイメージを与える
- 例:マイバッグの利用、省エネ設備の導入、社会貢献活動など
例
- テーマ: マイバッグの利用
- 具体的な取り組み: マイバッグ利用推進キャンペーン
- 共感を呼ぶポイント: 多くの人が取り組んでいる身近な問題
- 行動を促す提案: マイバッグを持ち歩く習慣を作る
- テーマ: 省エネ設備の導入
- 具体的な取り組み: 企業における省エネ設備導入
- 共感を呼ぶポイント: 企業の取り組みは社会全体に影響を与える
- 行動を促す提案: 自宅でも省エネ設備導入を検討する
- テーマ: 社会貢献活動
- 具体的な取り組み: 企業による社会貢献活動
- 共感を呼ぶポイント: 企業の社会貢献活動は地域社会に貢献する
- 行動を促す提案: 自分もできる社会貢献活動を見つける
4. 統計データやグラフを用いて現状を伝える
- 問題の深刻さを客観的なデータで示す
- 聴衆の関心を高め、問題意識を喚起する
例
- テーマ: プラスチックごみの削減
- 統計データ: 毎年800万トンものプラスチックごみが海に流出
- グラフ: 年々増加するプラスチックごみの量
- 効果: 問題の深刻さを客観的に示し、聴衆の関心を高める
- テーマ: 食品ロスの削減
- 統計データ: 世界で年間約13億トンの食品が廃棄
- グラフ: 途上国と先進国の食品ロス量の比較
- 効果: 問題の深刻さを客観的に示し、聴衆の意識を変える
- テーマ: エネルギーの節約
- 統計データ: 日本のエネルギー自給率は約10%
- グラフ: 年々増加するエネルギー消費量
- 効果: 問題の深刻さを客観的に示し、聴衆の行動を促す
5. 解決策を提示し、行動を促す
- 聴衆が取り組める具体的な行動を提案
- 問題解決への意欲を高め、行動を促す
例
- テーマ: プラスチックごみの削減
- 解決策: マイバッグやマイボトルの利用、プラスチック製品の使用量削減
- 行動を促す提案: 自分にできることから始め、周囲の人にも呼びかける
- テーマ: 食品ロスの削減
- 解決策: 食べ物余りの献立作り、賞味期限の確認、フードバンクへの寄付
- 行動を促す提案: 買い物リストを作って計画的に買い物をする
- テーマ: エネルギーの節約
- 解決策: こまめな電源オフ、省エネ家電への買い替え、公共交通機関の利用
- 行動を促す提案: 節電目標を設定し、達成する
データで説得力を持たせる:信頼できる情報で裏付ける
1. 信頼できる情報源からデータを取得する
- 国際機関、政府機関、研究機関、企業など
- データの出典を明示し、信頼性を高める
例
- 国際機関: 国連、世界銀行、OECDなど
- 政府機関: 総務省、環境省、厚生労働省など
- 研究機関: 東京大学、京都大学、日本経済研究センターなど
- 企業: トヨタ自動車、ソニー、パナソニックなど
データを取得する際のポイント
- データの出典が明確であること
- データの最新性、正確性、信頼性
- データの偏りがないこと
2. データを分かりやすく可視化する
- グラフ、図表、イラストなど
- データの傾向や意味を理解しやすいように
例
- グラフ: 棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフなど
- 図表: フローチャート、ピクトグラム、イラストなど
- その他: マップ、タイムライン、インフォグラフィックなど
可視化する際のポイント
- データの傾向や意味が分かりやすい
- 見やすく、分かりやすいデザイン
- 色や文字の使いすぎに注意
3. データをストーリーと組み合わせて伝える
- データだけ羅列するのではなく、ストーリーと合わせて伝える
- 聴衆の理解を深め、共感を呼ぶ
例
- テーマ: 地球温暖化
- ストーリー: 100年前に比べて平均気温が1℃上昇、このまま温暖化が進むと異常気象が増加
- データ: 過去100年間の平均気温の推移、異常気象の発生件数の推移
- 効果: データを単に羅列するよりも、ストーリーと組み合わせることで、聴衆の理解を深め、共感を呼ぶ
4. データの解釈について説明する
- データが何を意味するのか、どのように解釈できるのかを説明
- 聴衆の誤解を防ぎ、正しい理解を促進
例
- データ: 2030年までに世界のCO2排出量を45%削減
- 解釈: パリ協定の目標達成には、年平均3.7%の削減が必要
- 説明: データの意味を具体的な数値に置き換えて説明
- 効果: データの解釈を明確にすることで、聴衆の誤解を防ぎ、正しい理解を促進
5. データに基づいて結論を導き出す
- データを客観的な根拠として、結論を導き出す
- 聴衆の納得を得られるプレゼン
例
- テーマ: SDGs達成に向けた取り組み
- データ: SDGs達成には、年間約2.5兆ドルの投資が必要
- 結論: 政府、企業、市民が協力して、投資を拡大していく必要がある
- 効果: データに基づいて客観的な結論を導き出すことで、聴衆の納得を得られる
これらの例を参考に、データで説得力のあるプレゼンテーションを作成してください。
ストーリーで共感を得る:人の心を動かす語り口
1. 登場人物を設定する
- 問題に直面している人、解決のために努力している人など
- 聴衆が感情移入できるような人物
- 主人公: 環境問題に関心を持つ高校生
- 助っ人: 環境活動家、地元住民
- 敵役: 環境問題を軽視する企業、政治家
2. ストーリーの展開を工夫する
- 起承転結を意識
- 聴衆の興味を引きつけ、最後まで飽きさせない
- 起: 主人公は、プラスチックごみによる海洋汚染問題に深刻な関心を抱く
- 承: 主人公は、環境活動家や地元住民と協力して、プラスチックごみ削減キャンペーンを立ち上げる
- 転: キャンペーンは当初、企業や政治家から反発を受ける
- 結: 主人公たちの粘り強い努力によって、キャンペーンは成功し、プラスチックごみ削減条例が制定される
3. 感情に訴える表現を用いる
- 五感を刺激するような言葉、具体的な描写
- 聴衆の共感を得、心を動かす
- 五感を刺激する言葉: 美しい海、漂うプラスチックごみ、子供たちの笑顔
- 具体的な描写: 海に漂うプラスチックごみによって傷ついた動物、環境問題に苦しむ人々
4. 自身の経験や思いを込める
- 自身の経験や思いを語ることで、よりリアルなストーリー
- 聴衆の共感を呼び起こし、感動を与える
- 自身の環境問題への関心のきっかけ
- 環境問題に取り組むことによる喜びや葛藤
- 未来への希望
5. ハッピーエンディングを目指す
- 問題解決
- プラスチックごみ削減条例制定
- 環境問題への意識の高まり
- 主人公たちの成長
ユニークな切り口で差別化する: 記憶に残るプレゼン
1. 意外な視点からテーマを捉える
- 既存の枠にとらわれず、独自の視点でテーマを捉える
- 聴衆に新鮮な印象を与える
例
- 環境問題:プラスチックごみを減らすために、微生物を利用する
- 貧困問題:貧困層の経済活動支援に、AIを活用する
- 教育格差:オンライン教育で、教育機会の格差を解消する
2. ユーモアやエンターテイメントを取り入れる
- ユーモアやエンターテイメント要素を取り入れる
- 聴衆を楽しませ、飽きさせない
例
- SDGsに関するクイズやゲームを取り入れる
- SDGsをテーマにした歌やダンスを披露する
- 有名人をゲストスピーカーとして招く
3. 最新技術を活用する
- VR、AR、AIなどの最新技術を活用する
- 聴衆に没入感を与える
例
- VRを使って、開発途上国の現状を体験させる
- ARを使って、SDGsの目標達成に向けた取り組みを可視化する
- AIを使って、聴衆に最適なSDGsの取り組みを提案する
4. インタラクティブな要素を取り入れる
- 聴衆が参加できるようなクイズやワークショップ
- 聴衆の積極的な参加を促す
例
- SDGsに関するパネルディスカッションを開催する
- SDGsの目標達成に向けたワークショップを開催する
- 聴衆にSDGsに関するアイデアを共有してもらう
5. 自身の個性や強みを活かす
- 自身の個性や強みを活かしたプレゼンテーション
- 聴衆に印象を与え、記憶に残る
例
- 自身の経験を交えてSDGsについて語る
- 自身の得意な分野からSDGsの課題に取り組む
- 自身の専門知識を活かしてSDGsについて解説する
まとめ
ユニークな切り口で差別化するプレゼンテーションは、聴衆に新鮮な印象を与え、記憶に残る効果があります。上記の例を参考に、ぜひあなただけのユニークなプレゼンテーションを作成してみてください。
インパクトを与えるためのSDGsプレゼンしやすいテーマ別おすすめ例
- 環境問題: 地球温暖化、プラスチックごみ、森林破壊など
- 社会問題: 貧困、教育格差、ジェンダー平等など
- 経済問題: 持続可能な開発、経済格差、雇用問題など
- 国際協力: 開発途上国の支援、国際協調の重要性など
- 未来への展望: 2030年以降のSDGs、私たちができること
環境問題
1. 地球温暖化:
現状と将来予測
- 地球の平均気温は、産業革命以降約1℃上昇
- 21世紀末には、4℃上昇する可能性も
- 異常気象の頻度や強度が増加
- 海面上昇による沿岸地域の浸水被害
原因と影響
- 温室効果ガスの排出
- 二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素など
- 海面上昇、異常気象、生態系の変化
取り組み
- 温室効果ガスの排出削減
- パリ協定
- 再生可能エネルギーの導入
- 省エネルギー対策
個人や企業ができること
- 省エネルギー
- 公共交通機関の利用
- エコ商品の購入
- 企業における環境配慮

2. プラスチックごみ:
現状
- 年間約800万トンのプラスチックごみが海に流出
- 2050年には、海中のプラスチックごみの量が魚の量を上回る可能性
問題点
- 海洋生物への悪影響
- マイクロプラスチックによる人体への影響
- 環境汚染
取り組み
- 3R(リデュース、リユース、リサイクル)の推進
- プラスチックごみの削減
- プラスチックフリーの取り組み
個人や企業ができること
- マイバッグやマイボトルの利用
- 使い捨てプラスチック製品の使用削減
- リサイクル

3. 森林破壊:
現状
- 年間約1300万ヘクタールの森林が失われている
- 地球上の陸地面積の約10%が森林
原因
- 農地開発、木材伐採、鉱山開発など
影響
- 生物多様性喪失
- 地球温暖化
- 土壌流出
取り組み
- 森林保護
- 植林
- 持続可能な森林管理
個人や企業ができること
- FSC認証された木材製品の購入
- 植林活動への参加
- 森林保護団体の支援
4. 生物多様性:
- 生物多様性の重要性
- 生物多様性喪失の原因と影響
- 生物多様性保全に向けた取り組み
5. エネルギー問題:
- エネルギー問題の現状
- 再生可能エネルギーの導入
- 省エネルギー対策

社会問題
1. 貧困:
現状と将来予測
- 世界には約7億人が極度の貧困状態にある
- 2030年までに極度の貧困を半減する目標
原因と影響
- 紛争、自然災害、教育格差など
- 飢餓、栄養不良、健康問題、教育機会の喪失など
取り組み
- 貧困対策
- 経済成長、教育支援、社会福祉の充実
個人や企業ができること
- 寄付
- ボランティア活動
- フェアトレード商品の購入

2. 教育格差:
現状
- 世界には約2億6000万人の子どもが教育を受けられない
- 教育格差は貧困やジェンダー不平等などによって拡大
原因と影響
- 貧困、地域格差、ジェンダー不平等など
- 経済格差、社会格差の拡大
取り組み
- 教育格差の解消
- 教育へのアクセス改善、質の高い教育の提供
個人や企業ができること
- 寄付
- ボランティア活動
- 教育支援団体の支援
3. ジェンダー平等:
現状
- 女性は男性に比べて、政治、経済、社会など様々な分野で不平等な状況にある
原因と影響
- 性差別、伝統的な性別役割分担など
- 貧困、教育格差、健康問題など
取り組み
- ジェンダー平等の実現
- 女性のエンパワーメント
個人や企業ができること
- 性差別をなくす意識を持つ
- 女性の活躍推進
- ジェンダー平等を推進する企業や団体への支援
4. その他の社会問題
- 人権問題
- 差別
- 健康問題
- 移民問題
- 高齢化社会
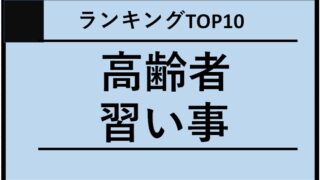
経済問題
1. 持続可能な開発:
現状
- 現在の経済活動は、環境や社会に大きな負荷をかけている
将来予測
- 地球環境の悪化、社会格差の拡大
取り組み
- 持続可能な開発
- 環境保護と経済成長の両立
個人や企業ができること
- 環境配慮型商品・サービスの購入
- エシカル消費
- 社会貢献活動
2. 経済格差:
現状
- 世界の富裕層1%が世界の富の半分以上を所有
原因と影響
- 貧困、社会不安定
取り組み
- 経済格差の縮小
- 累進課税、教育格差の解消
個人や企業ができること
- フェアトレード商品の購入
- 寄付
- ボランティア活動
3. 雇用問題:
現状
- 世界には約2億人が失業中
将来予測
- AIやロボット技術の発展による雇用喪失
取り組み
- 雇用創出
- 新たな産業の育成、教育・訓練の充実
国際協力
1. 開発途上国の支援:
現状
- 開発途上国は、貧困、飢餓、教育格差など多くの課題を抱えている
将来予測
- 開発途上国の課題解決は、世界全体の持続可能な開発に不可欠
取り組み
- 開発途上国の支援
- 経済援助、技術協力、人材育成
個人や企業ができること
- 寄付
- ボランティア活動
- フェアトレード商品の購入
2. 国際協調の重要性:
現状
- 地球規模の課題は、国際協力によって解決する必要がある
将来予測
- 国際協調が強化されれば、より多くの課題を解決できる
取り組み
- 国際協調の強化
- 国際機関の役割強化、国際条約の締結
個人や企業ができること
- 国際協力に関する情報発信
- 国際協力活動を支援する企業や団体への支援
3. その他の国際協力
- 平和構築
- 人権問題
- 環境問題
- テロ対策
- 感染症対策
未来への展望
1. 2030年以降のSDGs:
現状
- 2030年までのSDGs達成に向けて、多くの課題が残っている
将来予測
- 2030年以降も、SDGsの取り組みは継続される
取り組み
- 2030年以降のSDGsの目標設定
- 新たな課題への対応
個人や企業ができること
- SDGsの取り組みを継続する
- 新たな課題への解決策を提案する
2. 私たちができること:

現状
- SDGsの達成には、一人一人の行動が重要
将来予測
- 多くの人が行動を起こせば、世界を変えることができる
取り組み
- SDGsの目標を知る
- 日常生活の中でできることから始める
- 周囲の人々にSDGsを広める
個人や企業ができること
- SDGsに関する情報発信
- SDGsの取り組みを支援する企業や団体への支援
3. 未来への希望:
現状
- SDGsの取り組みによって、より良い未来を築くことができる
将来予測
- 持続可能な社会を実現
取り組み
- 一人一人が行動を起こす
個人や企業ができること
- SDGsの目標達成に向けて、行動を起こす
【まとめ】SDGs プレゼンしやすいテーマ選びの秘訣とは
- ターゲット層を特定し、聴衆の関心や日常生活に根ざしたテーマを選択する
- プレゼンの目的を明確にし、目的に応じたSDGsのゴールを選ぶ
- SDGsの17のゴールから適切なテーマを選定し、聴衆と目的に合致させる
- テーマを絞り込み、具体的な事例やデータを用いて説得力を高める
- 自身の関心や経験を取り入れ、熱意を持って伝える
- 地域や業界特有の課題を取り上げ、より身近な問題として共感を得る
- 信頼できる情報源から得たデータを分かりやすく可視化し、説得力を持たせる
- ストーリーを用いて、問題に直面する人々の経験を紹介し、感情に訴えかける
- ユニークな切り口や意外な視点からテーマを捉え、記憶に残るプレゼンを目指す
- ユーモアやエンターテイメントを取り入れ、聴衆を楽しませつつ重要なメッセージを伝える
- 解決策を提示し、聴衆に具体的な行動を促す
- 自身の経験や思いを込めたストーリーで、聴衆の共感と感動を呼び起こす
■■節約・関連■■
【関連記事】 ユニクロ・リサイクル: ボロボロの服でもOK!【関連記事】フードロスの取り組みは面白い!日本の効果的な戦略 【関連記事】趣味で節約を楽しむ方法:お金のかからない趣味のアイデア集 【関連記事】忍び寄るポイント泥棒!被害を防ぐための具体策 【関連記事】ポイント乞食の極意!貯め方と活用法完全ガイド 【関連記事】幹事がポイントを貯めるのはずるい?参加者の本音と解決策【関連記事】省エネで生きる: 家計に優しい10のエコ生活ヒント
■_■/ プレゼン装置はコチラから↓///
■■Amazonで見る【人気・まとめ記事】「生涯学習【科目別】」【人気・まとめ記事】「家族+」記事一覧【人気・まとめ記事】【連載・一覧】海外旅行の醍醐味を知る添乗員の旅行記&エッセイ【人気・まとめ記事】【定点観測】老後の資金がありません
【人気・まとめ記事】【人生100年・70歳のリアル出口戦略】親子2世代・NISA運用
【人気記事】孫の世話が楽になる!70代シニアの負担・不安ストレスをなくすためのガイド





